「ブックライティング実践講座」を読んだ
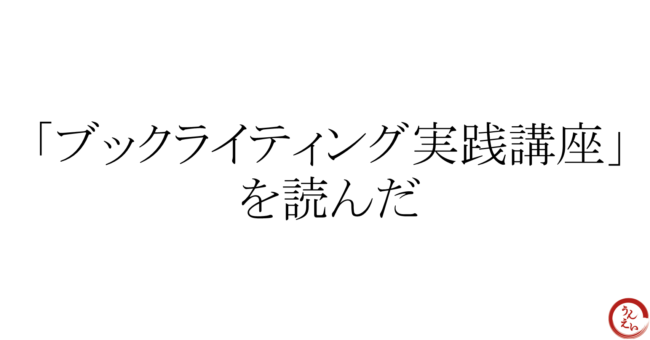
いつも大変お世話になっている西田かおりさんが書かれた本ということで読んでみました。私も本を書いたものの自己流でしたのでちゃんとした書き方を知りたかったですし。
※お知らせ
Amazon.co.jpの商品を紹介することで、紹介料を得られる「Amazonアソシエイト・プログラム」に参加しています。このリンクを通じてお買い物していただくと、私にも少しだけ紹介料が入ります(もちろん、みなさんのご負担は増えません)。
全体の感想
この本は、執筆の流れをとても丁寧に解説してくれていて、「本を書いてみたいな」と思っている人にとって、まさに実用的なガイドになっています。著者の方が、ご自身の経験をもとに語ってくれているので、机上の空論ではなくリアルな知恵が詰まっていますから。
読んでいて印象に残ったのは「原稿は書けるときに、力尽きるまで書く」です。やる気って本当に儚いものなので、いったん捕まえたときは力尽きるまでやっておきたいですよね。
知っておきたいこと
執筆に取り組むうえでの基本的な考え方や、心構えが紹介されています。中でも「その分野で著名になっている人が書いた本を買うか、自分の求めているものがタイトルになっている本を買うことが多い」という言葉がすごく腑に落ちました。読者は「この本が自分のためのものだ」と思えるかどうかがカギなんですね。
前述の「原稿執筆は体力勝負」という話もリアルでした。「頭を使って、ずっと座って、ずっと指を動かす」って、思っている以上にしんどいですよね。「体力がいらないなんて嘘」という一言には、うなずくしかありませんでした。書くことを本気でやるなら、まずこの現実をちゃんと知っておかないといけません。
ひとりのために書こう
「どんな人に向けて書くか?」という視点がとても大事だという話が出てきます。「多くの人に読んでほしい」と思って書いてしまいがちですが、それだとどうしても内容がぼやけてしまうんですね。たとえば、「副業の始めかた」というテーマなら、「会社員向け」ではなく、「都内のIT企業で働く35歳の男性。2歳の子どもがいて、住宅ローンの返済が始まったばかり」というふうに、読者像をできるだけ具体的に思い描くのがポイントです。
「たったひとりのために書くことで、逆に多くの人に刺さる文章になる」という話がありました。これは本当にその通りだなと感じます。また、「その道のプロであることを証明する」という視点も大切で、読者からの信頼を得るためには、自分の立場や経験をしっかり見せていく必要があるんですね。
執筆活動は持久戦
執筆は短距離走じゃなくてマラソンのようなものだ、という話が出てきます。最初はやる気満々でも、途中で息切れしてしまうことってありますよね。「書く時間がなかなか取れない」「家族の予定が入る」「仕事が忙しくなる」…そうした現実にどう向き合うかが、執筆を続けていくうえでのカギになると感じました。
特に「締切に向けて、土壇場で追い込みを書く」という話もリアルでした。時間の管理がうまくいかないと、最後に無理をすることになってしまう。だからこそ、計画的に進める力が求められるんですね。
そして、紹介されていた「〆切本」という本のタイトルと表紙が素晴らしすぎて買ってしまいました(笑)。
「どうしても書けぬ。」わかるわ~。
目次とプロットをつくろう
書籍の骨組みとなる「構成」の作り方が詳しく紹介されています。特に印象的だったのは、「独自メソッドが生まれないかを考えてみよう」という言葉です。「3ステップ」「○○メソッド」などの形式は、ビジネス書ではおなじみですが、それをただ真似するのではなく、自分の経験や視点をもとにした「自分なりの型」をつくることが大切だと語られています。
読者が読みやすいように情報を整理しつつ、自分らしさを盛り込んでいく。そのバランス感覚が、いい本をつくる秘訣なんですね。
原稿を書いていこう
実際の執筆プロセスが紹介されています。書き上げるまでのスケジュールが図でまとめられていました。
- 素材集め:約1ヶ月
- 目次立て・プロット作成:約1ヶ月
- 執筆・推敲・校正:約1~2か月
「本を書くのって半年くらいかかるんだな」と思うと同時に、内容によっては半年だとその間に変わってしまうこともありそうだなと…。iPadとApple Pencilを使って「立ったまま書く」というスタイルや、AIを執筆支援に使う話も面白かったです。
「自分の文章をAIに読ませて改善点を見つける」というのは私もやってます。
推敲と校正、本が出るまで
いよいよ仕上げのプロセスです。「原稿から一度離れて、頭を空っぽにして読み直してみる」というアドバイス、これはほんとうに大事ですよね。少し時間を置くことで、「あれ?ここ説明足りないな」とか「もうちょっと丁寧に書こうかな」といった気づきが出てきますから。
「締切に追われて、書き上げてすぐ提出」というのはできるだけ避けたほうがいいという話も納得でした。図や表の確認、校正など、本を出すまでにはいろんな作業があるんですよね。出来上がったものは寝かせて確認。これはいつも大事。
まとめ
執筆の現実が分かる本でした。
今はAIを使えばなんとなく文章は書けてしまいますし、ブログを書いている人も多いのですが、本となるとそうはいかないんですよね。企画して、素材を集めて、目次とプロットを作って書く。もちろん書くだけではなくて誰かの役に立つ内容で。そこまで書いてからも、推敲したり校正したりとやることはたくさんです。
漠然と本を出してみたいな~と思っている人は読んでみて下さい。
